| 事業報告及び計画 2024年度事業報告書 2025年度事業計画 |
|
2024年度事業報告書 2024年4月1日より2025年3月31日まで |
| [Ⅰ]事業の概要
各研究会・セミナーは、テーマ重複を避けるため全テーマを前年度末までに予め決定し、主としてWeb併用開催で年6回、若手懇談会は講師・参加者間の対話を図るために対面開催にて年4回、何れも計画通り開催した。平均参加者数は前年度比で研究会・セミナーは微減、若手懇談会はやや増加した。ニューガラス大学院は、できるだけ多数の方々に参加いただくと共に人的交流を図るため、Web併用開催とした。その結果、100名を超える参加者があり、講義では休み時間も含めて非常に多くの質疑応答がなされた。また懇親会も盛況で、講師を含む参加者間で活発な交流がなされた。機関誌については計画通り年3回刊行した。 1. ニューガラスに関する産業及び技術開発動向等の情報の収集及び提供 (定款 第4条第1項第1号関係) ニューガラスフォーラムの活動(研究会、セミナー、講演会)や外部学会等で得た技術開発動向や情報をホームページ、機関誌“NEW GLASS”を通じて会員へ情報発信した。 2.ニューガラスの産業及び技術開発等に関する調査 (定款 第4条第1項第2号関係) 2022年度に開始したガラス熔融プロセスにおける脱炭素化技術に関する調査事業を2024年度も継続実施した。国内外の関連技術の動向、特に全電気溶融、ハイブリッド溶融、水素燃焼、アンモニア燃焼、CCUS等についての公開情報を調査した結果を報告書にまとめ、2025年3月4日の報告会にて会員企業への説明を行った。2023年度と同じ形式で整理・報告したため、ガラス業界における対応状況や関連技術の推移を理解いただけたと考える。参加者は85名で、2023年度の21名から大きく増加した。2023年度は外部講師の講演を含む有料開催であったが、2024年度はニューガラスフォーラムからの報告のみとし、短時間化・無料化を行ったことが参加者増の一因と考える。 その他の活動として、2024年10月1日に日本エア・リキード合同会社イノベーションキャンパス東京の見学会を開催した。参加者は24名で、水素燃焼バーナーの実際の燃焼を見学し、また脱炭素化に対する取り組みを聴講した。 2024年11月26日にはオランダの研究開発団体GlassTrendとの共催セミナーを2023年度に引き続き開催し、欧州でのカーボンニュートラルへの取り組み状況を直接聞ける場をNGF会員へ提供した。Web併用形式で開催し、日本からの参加者は36名、海外からは100名を超える参加者があった。 また愛媛大学に寄付金を供与し、水素燃焼が泡の生成・成長やガラス物性に与える影響についての基礎的な研究を行った。ホットサーモカップル法という少試料・短時間の実験で泡生成のリアルタイム観察ができる手法を用いて興味深い結果が得られている。結果の一部をGlassTrend共催セミナーで講演いただいた。 3.ニューガラスに関する講習会、講演会、セミナー及び研究会等の開催 (定款 第4条第1項第4号関係) (1)研究会の開催 ・ ガラス科学技術研究会(主査:愛媛大学 斎藤 全 教授) ・ 評価技術研究会(主査:豊橋技術科学大学 武藤浩行 教授) ・ ニューガラスセミナー(主査:滋賀県立大学 松岡 純 教授) 2024年度は予定していたガラス科学技術研究会を2回、評価技術研究会を2回、ニューガラスセミナーを2回の計6回全てを開催した。評価技術研究会では2019年以来となる見学会を実施した。見学会を除く平均の参加者数は32名と2023年度の36名から若干減少した。開催形式はハイブリッド開催を主とした。 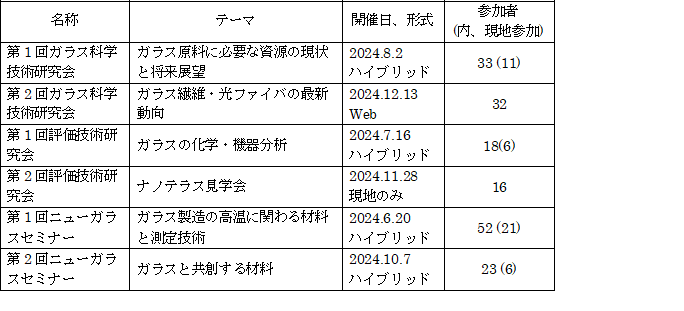 各研究会・セミナー間でのテーマや開催時期の重なりを避けるため、年度内に各主査とすりあわせを行って2025年度のテーマと開催時期を決定した。 (2)講座の開催 ニューガラス大学院 (委員長:北海道大学 忠永 清治 教授) ガラスの研究・開発・製造・応用に携わる人材の育成に寄与するため、大学教員や企業の研究者・技術者等の各分野の講師による計17テーマの講座を、基礎課程として10月17、18日、応用課程として10月31日、11月1日の計4日間開催した。ニューガラス大学院は、単に講義を聞くだけでなく、講師と意見交換することも目的の一つである。 2024年度も、基礎課程では材料科学からガラスの諸物性について、また応用課程では、ご好評をいただいている製造フローに沿っての各技術の講座とした。本年は17テーマ中4テーマで新講師が担当した。2023年度に実施した機械学習・マテリアルインフォマティックスに関する特別講座に関しては、2023年度のアンケートの結果、生徒の予備知識に大きなバラツキがあり、初心者と経験者の両方に満足のいく講義が難しいと考え、2024年度以降はテーマから外すこととし、個別形態での講座を検討することとした。 本年も昨年に引き続き、AGC ものづくり研修センターをお借りして対面と Web のハイブリッド方式で実施した。運営についてはAGC 社員のご協力もいただいた。2023年度に課題であった当該研修センターの会議システムの音響・通信状況は対策により改善し、ハイブリッド方式での講義は問題なく実施できたと考える。遠方からでも Web で容易に参加できる利点があるほか、講師からも対面形式は講義しやすいとの感想をいただいた。講義では現地および Web 両方の受講生から多くの質問があったほか、休み時間にも講師への質問者の列ができており、現地参加の受講者にとって有益なものであったと思われる。 受講者は計 107 名であり、計画(90 名)を上回った。昨年度の計 121 名より多少減少したものの、その多くが学生受講者の減少によるものであり、また今年度より参加費の消費税を頂くこととしたことから、収支は改善した。 基礎課程 1 日目終了後の懇親会も盛況で、講師・受講者および受講者間で活発な交流が行われた。 本大学院を社員の教育研修に組み込んでいただいている企業もあることから、今後、他の企業の人事部等へも社員教育に活用いただける様、その有用性を説明していきたい。 (3)若手懇談会の開催 (会長:HOYA(株) 伊藤 陽祐) 2024年度は2023年度と同様に意図して通年テーマは設けず、「興味を広げる」という方針に基づき講演会はサブテーマのみを設定し、計画通り4回開催した。開催方法については、この会の目的の一つである講師ならびに参加者間のコミュニケーションを図るということから全て通常開催とした。年間の参加者は平均25名/回であり、2023年度(21名/回)に比較してやや増加した。講義後のアンケートでは、すべての講演について満足度は90%を超えていた。また、導入として基礎的な講演を行った後に応用講演を行う形式は、基礎的な部分を理解することで、応用的な部分をより深く理解することができ、95%以上の方が満足であるという回答であった。 役員会は産・学より選出された役員(11名)により講演会の企画ならびに運営が行われ、年4回開催した。 各回のテーマ、日程及び開催方法は以下の通りであった。 第153回若手懇談会:ガラスの着色 (2024.05.10)通常28名 第154回若手懇談会(見学会):自動実験装置 (2024.07.03)通常20名 第155回若手懇談会:ガラス製造プロセスのシミュレーション技術 (2024.10.15)通常 21名 第157回若手懇談会:ガラス溶解部材(耐火物、貴金属) (2025.02.07)通常 29名 (4)見学会の開催 会員企業のガラス関連施設を訪問する見学会は企業間の制約が多く実施に至らなかった。 4.ニューガラスに関連するデータベースの構築、維持及びその提供(定款 第4条第1項第5号関係) 2024年度もデータの収録充実に注力し、年間約7,300件の新規登録を行った。その結果、3月末時点における収録ガラス数(特性・構造データの総計)は、約40.5万件となった。データベースの更新は、4月、9月、1月の3回実施した。8月にはサーバー環境の変更に対応するため、新OSのインストールを行った。併せて2024年度の開発項目としてシステムの改良を行い、3月末時点でVer8.3.1.8が最新のシステムとなっている。 普及のためのPR活動として、2024年度も基礎講習会を6月に、応用講習会を11月にWeb開催した。 本年度、INTERGLADのWebアプリケーションの検索メニューから、自動的に大量のデータをダウンロードするインシデントが発生した。データベース保護の観点から、セキュリティレベルを改善する必要があると判断し、直ちに暫定対策を実施した。現在、対策方法の調査を継続しており、2025年度の早い時期に更にレベルの高い対策を行う予定である。また、利用者側の不適切な使用を防ぐため、新規にINTERGLAD利用規約を制定してデータ抽出の制限を定め、利用者側に周知することをNGFデータベース委員会にて検討した。 一方、本事業を将来に渡って継続していくためには、経常赤字から脱却するとともに、多くの費用を必要とするシステム更新(不具合改善および利便性改善、サーバー更新対応、セキュリティ対策など)、およびガラスに関する専門的知識を必要とするデータ入力技術者の確保を継続的に進めていく必要がある。この対応の一環として、2024年度に海外ユーザを主な対象としてデータ入力単価の見直しを実施したが、本事業の持続性を確保するために、NGF会員・大学を含めた国内INTERGLADユーザ会費に関して必要な価格改訂を行うと共に、使用頻度の多いヘビーユーザーに応分の負担を求める課金方法の導入を検討している。2025年度に関係者に諮り、2026年度4月からの価格改訂に繋げたい。 5.ニューガラスに関連する産業及び科学技術に関する機関誌の発行 (定款 第4条第1項第6号関係) 機関誌“NEW GLASS”の発行 (編集委員長:名古屋工業大学 早川 知克 教授) ニューガラスに関する国内外の新製品・新技術の紹介、内外のニュース、関連産業の動向、技術解説を内容とした機関誌“NEW GLASS”を、2024年度は計画通り年3回刊行し、会員ならびに定期購読者(約70名)他に提供した。編集委員会は充実した企画内容ならびに構成を実現すべく機関誌の企画、編集を行い、年3回開催した。特に、特集は事前にテーマ、執筆者候補を挙げ、より深く議論することにより、その充実を図った。2024年度の特集のテーマは以下の通りであった。 第142号(2024年07月01日刊行):「計算科学を活用したガラスの研究」 第143号(2024年11月01日刊行):「ガラス製造における脱炭素化技術」 第144号(2025年03月01日刊行):「健康を支えるセラミックス・ガラス材料」 7.ニューガラスに関する標準化・規格化の調査研究 (定款 第4条第1項第7号関係) (1)JIS R 3252-1994「ガラスのレーザ干渉法による均質度の測定方法」 日本光学硝子工業会が事務局となってJIS原案作成委員会が発足し、NGFは中立の委員として参加している。2024年度は3回の会合に参加し、原案は8月にJSAに提出された。 (2)標準化委員会再開に向けた活動 NGFが所管するJISが6件あり、これらの定期見直し及び改正時の実務を組織的に行うべく標準化委員会を再開すること、それに向けて準備ワーキンググループにて標準化委員会の構成・役割等を議論することが2024年12月の理事会で承認された。 準備ワーキンググループを編成するとともに、ワーキンググループの議論を受けて、委員長および委員を打診中である。 8.ニューガラスに関連ある内外の団体、学会及び研究機関との交流及び協力 (定款 第4条第1項第8号関係) (1)経済産業省、NEDO及び材料関連6団体との情報交換会については、2024年度は開催 されなかった。 (2)GICの活動として、例年通り、環境広報部会、環境技術部会、プロセス・材料技術部 会、ガラス研究振興部会の委員並びに事務局として参画し、Topインタビューの企画・遂行、環境に係わる諸活動及び運営事務局としての活動等を予定通り実施した。また、青少年のための科学の祭典 大阪大会に説明員として参加・協力した。 (3)GICシンポジウムが2024年11月7日に通常開催され、NGFメンバーも事務局として 準備・運営に協力した。「未来につながるガラスの研究開発・生産技術」というテーマ で3件の招待講演とポスターセッションが開催され、活発な討議が行われた。講演会 場も満員の盛況であり、アンケートでもかなりの高評価を頂いた。 9.前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業 (定款 第4条第1項第9号関係) (1)気中溶解技術の普及 NEDOプロジェクト「革新的ガラス溶融プロセス技術開発」(2008~12年度)の国内企業への成果普及活動を継続している。2024年度はガラス及びフォトニクス材料討論会でポスター発表するなど紹介活動を行ったが、新たな導入実績は無かった。 (2)ガラス研究振興事業 大学等における若手・中堅の研究者によるガラスの学術的研究に対して産業界から支援を行い、ガラス材料に関する基礎的研究の推進を後押しし、ガラス材料研究者の確保・育成を図ることを目的として、GICと共催で「ガラス研究振興プログラム」を立ち上げ、2022年度から研究助成を開始した。2022・23年度の採択研究者からは、助成金を初年度に一括提供する点や研究期間が3年であることが装置導入のし易さや基礎研究に挑戦できる点で高評価を頂き、また、審査委員からも周囲の分野を巻き込む将来の研究展開の起点となるような成果に繋がるなどの期待も頂き、本プログラムがガラス研究振興および研究人材の確保・育成という当初の目的に大きく寄与し始めているとの第一期の認識のもと、2024年度は第二期初年度となる2025年度向けの研究テーマ募集活動を行った。 2024年度向け研究テーマに関しては、2024年1、2月の審査会にてエキスパートコース1件、チャレンジコース2件が採択されていたが、2024年5月に助成金を支給して研究がスタートした。6月の総会で研究助成金授与式を、また12月に意見交換会を実施した。この意見交換会では非常に活発なご議論をいただき、採択テーマの研究者にとっても有意義であったとのコメントを頂いた。意見交換会の資料および質疑応答は冊子にまとめ、審査員、GICガラス研究振興部会委員、NGF研究振興委員、およびスポンサー各社にお配りした。 2024年度向けの募集では、広報活動に注力し大学等への周知に努めた結果、応募が前年度よりも大幅に増加したことから、2025年度向けの募集についても広報活動に力を入れ、学会への案内、全国176の大学・公的研究機関への案内、ポスター掲示や各大学の助成金リストへの掲載を進めるとともにWeb説明会を実施し、本プログラムの認知に努めた。 これらの活動の成果により、2025年度向け募集では最終的にエキスパートコース5件(前年と同数)、チャレンジコース11件(前年より5件増加)と本事業が特に期待する他分野からのガラス分野への参入提案件数が大きく増加した。 その後、2025年1月~3月に研究審査会を開催し、厳正な審査の結果、3月末に2025年度採択テーマとして、以下の通り、エキスパートコースで1件、チャレンジコースで1件、調査研究2件の採択が決定された。 <エキスパートコース> テーマ;酸硫化物における特異的なユニット形成と結晶化速度が及ぼすガラス化挙動への影響解明 申請者;北海道大学 大学院理学研究院 化学部門 助教 奈須 滉 助成額;700万円(3年間) <チャレンジコース> テーマ;無容器法としての火炎プロセスで切り拓くニューガラスサイエンス 申請者;広島大学 大学院先進理工系科学研究科 助教 平野 知之 助成額;700万円(3年間) <調査研究(非公開)> エキスパートコースから 1件 助成額 85万円(1年間) チャレンジコースから 1件 助成額 85万円(1年間) (3)ガラスの本(新版)の発刊 2025年7月のNGF創立40周年を記念する事業の一環として、日刊工業新聞社から、長岡技術科学大学 教授 本間 剛 先生を代表執筆者、NGFを編著者として、「ガラスの本(新版)」を2025年3月19日に発刊した。執筆には、代表執筆者の本間先生を始めとするガラス分野の先生方とNGF会員企業の専門家にご尽力頂いた。 発刊の目的は、若い世代の方々にガラスについて興味を持って頂き、将来ガラスに関わる人材を増やすことである。本の難易度としては、「専門家ではない文系の大学生程度で理解できるもの」とし、「わかりやすい、理解しやすい」ということを基本コンセプトとした。今後、上述の目的のために、この本を有効活用していきたい。 本書籍は新入社員への基礎教育ツールとしても適していると思われることから、NGF会員の皆様には、是非ご活用頂きたいと考えている。 [Ⅱ]業務執行ならびに事務局の概要 1.定時総会 2024年6月27日に(一社)ニューガラスフォーラム第14回定時総会をWeb併用形式にて開催した。 議決数:正会員14法人 議決事項 第1号議案 2023年度事業報告案ならびに収支実績案及び決算案の件 第2号議案 2024年度事業計画案ならびに収支予算案の件 第3号議案 会費の改定案の件 第4号議案 2024年度・2025年度役員(理事・監事)選任案の件 第5号議案 規約の制定改廃の件 定款 2.理事会 2024年6月5日に第36回理事会をWeb併用形式にて開催した。 審議事項 第1号議案 2023年度事業報告案ならびに収支実績案及び決算案の件 第2号議案 2024年度・2025年度役員(理事・監事)選任案の件 第3号議案 規約の制定改廃の件 定款 第4号議案 2024年度・2025年度特別会員選任案の件 2024年6月27日に第37回理事会を開催した。 審議事項 第1号議案 2024年度・2025年度役員(会長・副会長・専務理事)選任案の件 2024年12月17日に第38回理事会をWeb併用形式にて開催した。 審議事項 第1号議案 2024年度事業計画の進捗状況と今後の対応の件 第2号議案 2024年度収支予算の進捗状況と今後の見込みの件 第3号議案 「標準化委員会」再開に向けた準備活動開始の件 2025年3月18日に第39回理事会をWeb併用形式にて開催した。 審議事項 第1号議案 2025年度事業計画案の件 第2号議案 2025年度収支予算案の件 第3号議案 規約の制定改廃案の件 「GE-310 特別会員規程」 3.事務局 2024年4月1日現在の役員・職員は常勤役員1名・出向職員3名・嘱託職員6名・派遣職員0名・出向研究員0名・嘱託研究員0名・補助研究員0名の計10名であった。 2025年3月31日現在の人員は常勤役員1名・出向職員2名・嘱託職員6名・派遣職員0名・出向研究員0名・嘱託研究員0名・補助研究員0名の計9名となっている。 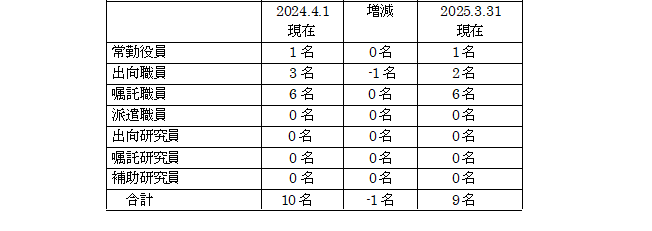 以上 |
|
|