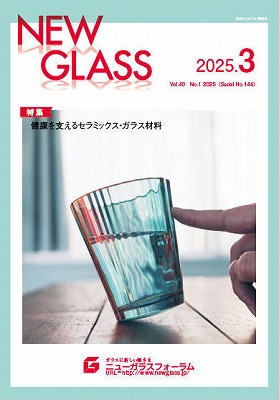
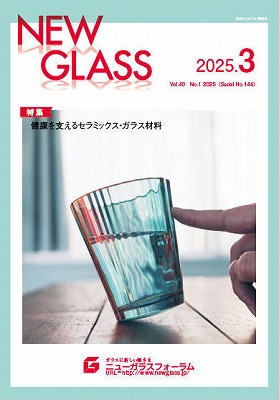
巻頭言科学における「味」と「心」 ------- p.1 [試し読み] おにぎりほど,その味に作り手の個性が反映される食べ物はないだろう。白米と塩,海苔だけの一番単純なおにぎりでも,実家の母と私の妻のつくるものとでは,とても同じ具材から出来ているとは思えないほど,形はもちろん,味も風味も異なる。素材はほとんど変わらないのに,なぜこれほどに味が違うのだろうか。もし,味が素材の成分だけで決まるとすると,この事実は説明できないであろう。おそらく,おにぎりを食べるときは,単に素材の味だけでなく,作り手の気持ちや握るときの情景などを含めた「心」も含めて味わっているのではないかと思う。
神戸大学大学院理学研究科 化学専攻 内野 隆司
特集「健康を支えるセラミックス・ガラス材料」1)炭酸アパタイト人工骨 ------- p.3 [試し読み] 残念ながら人工骨でも,誤認,事実とは異なる教育が行われていた。骨の無機組成は炭酸アパタイトである。ものづくりより組成分析が容易であり,1970 年代にハイドロキシアパタイト焼結体が人工骨として臨床応用されるずっと前から骨の無機組成が炭酸アパタイトであることは知られていた。次に,骨の無機組成が炭酸アパタイトである理由を述べる。
九州大学大学院 石川 邦夫
2)免疫系に積極的に働きかけるバイオセラミックスの創製とその抗腫瘍効果 ------- p.21 [試し読み] 我が国の死亡率の第1位は1980年以来,悪性新生物(がん)であり,総死亡率の30%を越えている。最近,従来のがん三大療法(外科療法・放射線療法・化学療法)に加えて,副作用がほとんどない・がんの部位を選ばない・三大療法との併用が可能などの理由から「免疫療法」が注目され,着実な成果をあげてきている。免疫療法には,患者の体に免疫賦活剤などを投与して免疫細胞を活性化させてがんを治療する「能動免疫療法」および患者自身の免疫細胞を体外(in vitro)で培養・活性化させてから再び患者にその免疫細胞を戻して体内の免疫細胞を活性化させてがんを治療する「受動免疫療法 (養子免疫療法)」がある。
明治大学 相澤 守 他1名
3)スパッタ法による非晶質リン酸カルシウムコーティング膜の作製とAg添加による抗菌性の付与 ------- p.25 [試し読み] 硬組織代替デバイスには骨との強固で迅速な結合が求められる。そのため,リン酸カルシウムを用いたコーティングは,リン酸カルシウムの優れた骨適合性とチタンの機械的特性の両方の長所を生かした有効な手法である。特に,プラズマスプレー法によるハイドロキシアパタイト(HAp)コーティングは,成膜速度やコストの観点から実用化されてきた。しかし,プラズマスプレー法は高温プロセスであるため,コーティング膜質の制御が容易ではない。加えて,HAp は中性溶液中で最も安定なリン酸カルシウムであり,生体内での溶解性が低い。このため,生体内埋入後においてもHAp コーティング膜はほとんど溶解せず,安定してデバイス表面に残存する。そのため,チタン製デバイスはHAp コーティング膜を介して骨と結合するが,チタンの特徴であるオッセオインテグレーションを十分に発揮できているとは言いがたい。
東北大学大学院 上田 恭介 他1名
4)中間酸化物を活用した生体用リン酸塩ガラスの創製 ------- p.31 [試し読み] 当研究グループは,無機イオンによる細胞活性化機能を付与した生体用ガラスの創製に向けて,リン酸塩ガラスに注目している。リン酸塩ガラスはケイ酸塩ガラスと比べ酸性度が高く,様々な無機成分を幅広い範囲で導入することが可能である。加えて,ケイ酸塩ガラスと比べ,比較的少ない網目形成酸化物を含む組成でもガラス化するため,より多くの無機成分をガラス網目構造中に取り込める特徴がある。しかし,一般的なメタ組成のリン酸塩ガラスは,過剰なリン酸イオンを溶出することで周辺を酸性化し細胞機能を阻害する。一方,様々な細胞活性化機能を有する無機イオンにおいても過剰な場合に細胞機能を阻害する可能性がある。よって,リン酸塩ガラスを母材に無機イオンを導入した生体活性ガラスを創成するには,厳密な無機イオン溶出挙動の制御が必要である。
産業技術総合研究所 李 誠鎬
研究最先端不均一弾性体理論を利用したボゾンピーク解析およびガラスの中距離秩序との関係 ------- p.39 [試し読み] "ガラス形成物質において,音波の終わりの周波数帯であるテラヘルツ(THz)帯でボゾンピーク(boson peak, BP)と呼ばれる普遍的な励起が観測される。BPは,結晶音波を記述するデバイモデルから逸脱した過剰な振動状態密度(v-DOS,g (ω))として観測される。デバイモデルのv-DOS は,D次元物質の場合ωD-1(ωは角周波数) に比例するため,BP はg(ω)?ωD?1スペクトルにおいてピークとして現れる。 BPは,結晶に比べて極めて低いガラスの熱伝導率およびガラスのTHz帯の光吸収端など,ガラス材料に関連する身近な現象の起源あるいは引き金となっている。BP励起はガラスの熱的,機械的,光学的特性に大きく寄与しており,そのメカニズムの理解と応用が期待されている。"
筑波大学 森 龍也 他1名
東京科学大学 Soo Han Oh 他1名
大阪大学・立命館大学 藤井 康裕
東京大学大学院 水野 英如
物質・材料研究機構 小原 真司
ニューガラス関連学会1)第65回ガラスおよびフォトニクス材料討論会参加報告 ------- p.44 [試し読み] 2024年11月7日と8日の2日間,福岡県福岡市のアクロス福岡にて第65回ガラスおよびフォトニクス材料討論会が開催された。今回は第20回ガラス技術シンポジウム(GIC20)も共催で行われ,「未来につながるガラスの研究開発・生産技術」をテーマとし3名の先生方に登壇いただいた。また,藤野先生(九州大学),村田先生(熊本大学)をはじめとする実行委員会の皆様による円滑な運営のもと,多数の研究発表と活発な議論が行われた。本稿では,筆者の印象に残ったいくつかの講演について報告させていただく。
京都大学大学院 手跡 雄太
2)第65回ガラスおよびフォトニクス材料討論会参加報告 ------- p.47 [試し読み] 初日は隣に並んだA 会場とB 会場をつなげて大会議室とし,午前は倉田元治学生賞の選考を兼ねた博士課程の学生による3件の英語での一般講演が行われた。午後はポスター会場にてガラスやフォトニクス材料に関わる基礎科学および技術,企業の製品・技術紹介,ガラスに関係する?学等の研究室紹介という3つのテーマにてポスターセッションが行われた。発表件数は合わせて61件であった。その後,再度AB会場にて第20 回ガラス技術シンポジウム(GIC20)として3件の講演が行われた。その後,学会会場の向かいのレストランにて懇親会が行われた。
AGC(株) 西條 佳孝
3)第20回ガラス技術シンポジウム報告 ------- p.49 [試し読み] 2024年11月7日に第20回ガラス技術シンポジウム(以下GIC20)が,第65回ガラスおよびフォトニクス材料討論会(以下ガラ討)との共催で開催された。本会は,九州大学の藤野研究室でお世話いただいた。本シンポジウムを企画運営した,GIC(ガラス産業連合会)は,ガラス産業に関連する6団体より構成され,2000年3月に発足した団体である。産学官の連携促進活動の一環として本シンポジウムを開催しており今回で20 回目となる。2022年国際ガラス年を機にホームページを一新し,Web 版工場見学ツアーやガラスミュージアム等コンテンツを充実しているので,是非一度HP を訪れて欲しい。
石塚硝子(株) 吉田 幹
新商品・新技術紹介酸素水素燃焼でガラスを溶融した場合のガラス品質への影響 ------- p.52 [試し読み] 水素を燃料として利用する場合では,大きく分けて燃料電池等を介して電力に変換する方法と,直接燃焼させる方法の二通りの方法がある。すでに電気硝子業界では全電気溶融法の採用実績があるため,水素を電力として利用するのであればガラス溶融過程での開発要素は少ないと言える。しかし,無アルカリガラスなど一部のガラスはそもそも電気を通さないため,全電気溶融法を採用することができない。またガラス溶融窯の規模が大きく生産量変動も大きなびんガラス業界では,ブースタ電極が引き起こす上昇・下降流によって溶融ガラス表面に浮かんだ泡がガラス内部に引き込まれ,製品品質が悪化するため全電気溶融法への転換が困難だとされている。このためガラスメーカすべてが電気溶融法に移行することは難しく,水素を直接燃焼することによってガラスを加熱する手法が残ると考えられる。
東洋ガラス(株) 東條 誠司
関連団体2025年「ガラス産業連合会新年会」報告 ------- p.56 [試し読み] 2025年1月24日(金),ガラス産業連合会新年会が東京都千代田区の如水会館にて通常開催されました。経済産業省,学界,会員企業,関連団体,報道機関等,270名の方々にご参加いただき,盛況となりました。この新年会はガラス産業連合会に加盟する一般社団法人板硝子協会,硝子繊維協会,電気硝子工業会,一般社団法人日本硝子製品工業会,日本ガラスびん協会,および一般社団法人ニューガラスフォーラムの6団体で主催しており,今年は硝子繊維協会の伊藤専務理事の司会で行われました。
(一社)ニューガラスフォーラム 事務局
コラムなんて素敵な吹きガラス ------- p.61 [試し読み] 吹きガラスっておもしろい! 最近そう思えるようになってきた。吹きガラス教室に通い始めてレッスンは100回を超えた。まだまだ思うようにならないけれど,作業にもすこし慣れてきて,いろいろな形や色模様の作品ができあがる。ガラス会社に入り研究開発部門に配属されたので,入社して10年間くらいはさまざまな組成のガラスを坩堝で溶かして流しだし,ガラスの板を作ってはその特性を測ってきた。溶かしたガラスは物性を知るための試料だった。その後は管理者になり自らガラスを溶かすことから遠ざかった。ガラスは広い組成範囲で多様な特性を持つというすばらしい材料であるとともに,いろいろな大きさや形状を作ることができるという特長がある。会社を離れ時間ができたのを機に,自分で溶けたガラスから形のあるガラスを作ってみたいと思って始めたのが吹きガラスである。
滋賀県立大学 山本 茂